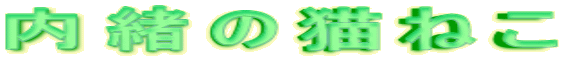
「雪村……暇か?」
突然斎藤さんに声をかけられて、掃除をしていた手を止めた。
「どうかしたんですか?」
首をかしげて私は問うた。
斎藤さんから話しかけてくれるなんて珍しい。
「いや……時間があればでいいのだが……」
なんだか言いにくそうに、視線も合わさずに……
「時間ならいつでも空いてますよ。何かお手伝いできることがありますか?」
あの斎藤さんのことだからきっと何かあるのだろう。
言いにくそうなのは私に何か頼みがあるのかと踏んで聞くけれど、
「別に何かやってほしいわけじゃない」
何と言えばいいのか……と考えているらしい斎藤さん。
結構長く共に居るはずだけど、未だに斎藤さんは私に話すのが苦手みたいで……もっと普通に話せたらといつも思ってしまう。
「えっと……じゃあ暇ですけど…」
「ならば、ついてこい」
「斎藤さん!?」
こっちだ。と私を振りかえることなく歩いて行く彼に、慌てて雑巾を放り出した。
勿論、あとで片付けておきます……
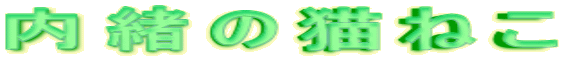
斎藤さんに連れられて来た場所は、屯所の裏。
誰も手入れをしないのか草木が鬱蒼としている。
「斎藤さん?こんなところで何を……」
「静かにしろ」
咎めるような視線と言葉に思わず口を押さえた。
「……こっちだ」
すると斎藤さんが私を手招きする。
それに導かれるように奥へ進むと………
「ニャァ」
愛らしい声が聞こえた。
「えっ…猫?」
見れば真っ黒い猫が斎藤さんの足にすり寄っているではないか!
「…雪村、猫は嫌いか?」
そう言って猫を抱き上げる斎藤さんは……
「……っ///」
普段絶対見れないような優しい顔で……
「雪村?」
「………///」
いいもの見た……!!
「どうした?猫は嫌いか?」
「い、いえ!大好きです!!」
ブンブンと頭を振ればふっと斎藤さんが笑った。
「あんたならそう言うと思った」
「もしかして…この子を見せるためにここに…?」
「ああ」
頷いてこの猫のことを話してくれた。
なんでも見回り中に懐かれて付いて来たらしい。
妙に人懐っこい猫で、そのままここに住み着いてしまったのだと斎藤さんは言った。
「副長には黙っておいてくれ…」
ばつが悪そうに言う斎藤さん。
彼が土方さんにこんな秘密を隠してるなんて思ってもみなかった。
それに……
「意外ですね」
「意外?」
「はい。斎藤さんは面倒見がいいんだなぁって」
そう言うと、俺は何もしてはいないと顔をそむける斎藤さん。
「でも……この子は斎藤さんのこと大好きみたいですね」
斎藤さんの腕の中でゴロゴロと喉を鳴らす猫。
……ちょっと猫が羨ましい。
「あんたも抱けばいい」
私の視線を勘違いしたのか斎藤さんが猫を私に差し出す。
私も受け取ろうと手を伸ばした……が、
「ニャー!」
「わ、わ!?」
いきなり飛びかかってきた猫。
それに驚いた私は情けなくも体勢を崩し、ひっくり返ってしまった。
「…っ!?」
「痛たた…」
尻もちをついたせいでお尻が痛い……
斎藤さんもまさかこうなるとは思っていなかったのか、目を見開いていた。
そして飛びついてきた猫は……
「ニャァ…」
また斎藤さんの足にすり寄っていた……
「大丈夫か?雪村」
「なんとか……」
まだお尻は痛いですけども。
「私、嫌われちゃったみたいですね……」
「………すまない」
わりと動物には好かれる方だと思っていたのにな。
ちょっと落ち込む私になぜか斎藤さんが謝る。
「斎藤さんが謝る必要なんて無いですよ!」
「しかし俺がここに連れてきたんだ。責任の一端はある」
そう言うとしゃがんで猫を撫でながら溜息をついた。
その手に嬉しそうに頬をすりよせる猫。
「………」
いいなぁ……
「……雪村?」
「え!?は、はい!」
気持ちよさそうに撫ぜられている猫をみて、ついついぼーっとしてしまって斎藤さんの話を流してしまった。
「気分を害したか…?」
「い、いえそんな…!」
まさか猫に嫉妬なんて言えるわけもない。
でも……やっぱりいいなぁ。
あんな風に撫でてもらえるなら猫になりたい……
「……すまん」
またもや猫を羨んでいると斎藤さんがなぜか頭を下げた。
「さ、斎藤さん!?」
「俺はただ雪村が喜ぶと思ったんだが……」
そう言って俯く斎藤さん。
その気遣いに胸がジーンと熱くなる。
「あ、あの大丈夫です!私、此処に連れてきてもらえただけで十分嬉しいです!」
「だが……」
「だって斎藤さんが土方さんにも言えない秘密を私に教えてくれたんでしょう?それって凄く嬉しいですよ!」
ちょっと勢いをつけ過ぎたか、斎藤さんが驚いた様だったけど……
「……あんたは変な女だな」
そう言って彼は苦笑した。
今、斎藤さんは用意していたのだろう干物を猫にやり、それを食べる猫を撫でている。
猫を撫でる斎藤さんを見ているのは楽しい。
でも手持ち無沙汰は変わらず、しかも猫に嫉妬してしまったりするのを斎藤さんに知られれば恥ずかしいことこの上ない。
でも、折角斎藤さんと過ごせるのだ。帰るわけにもいかないし……
そんな悶々とした気持ちで斎藤さんと猫を見ていた私の耳に、猫の鳴き声が聞こえた。
「ニャァ」
よくよく見るとその声はあの黒猫ではなく……
「あれ?」
「来たか」
いつの間にか二匹の猫が仲よさそうに並んでいた。
「猫は一匹じゃなかったんですか?」
「元はあの黒猫だけだった」
私を嫌っているらしい黒猫の横には灰色の猫。
もしかして……
「あのオス猫はどこからともなく現れた」
ちょっと不貞腐れたような言葉に聞こえるのは私だけだろうか?
「あの黒猫、メスなんですか?」
「そうだ」
楽しそうにじゃれ合う二匹。それをなぜか睨むように見ている斎藤さん。
もしかして……
「斎藤さん…嫉妬してるんですか?」
なんとなくそう思った。
「何を…」
「だって…凄く嫌そうな顔してますよ?」
「お、俺は別に……」
なぜか焦る斎藤さん。いつも冷静な彼らしくない。
そんなことを思っているといつの間にか足もとに一匹の猫。
灰色の方だ。
「ニャア」
ゴロゴロと私にすり寄る灰色の猫。
そして……それをじっと見ている黒猫。
……と、斎藤さん。
「こっちの猫は私のこと気にいってくれたみたいですね」
そう言って頭を撫でようとした時、
「千鶴」
「わ!?」
斎藤さんが私の手を掴んだ。
それに…今、名前で……「ニャア!」
「え?」
斎藤さんが私の名前を呼んでくれた瞬間、別のところから返事があった。
それは……私達の足もとから。
「黒…猫…?」
「………」
………
…
「千鶴」
「ニャア!」
試しに自分の名前を言ってみるとまた返事をした。
これは……
「斎藤さん?」
「……何も言うな」
斎藤さんの顔を見ればその目もとは…赤く染まっていた。
それを隠すように私に背を向けた斎藤さんは水を汲んでくると足早に去っていき……
私と二匹が残されてしまった。
「えっと……千鶴?」
「ニャア」
黒猫は呼べば答えたが、頭に触れようとしたら拒まれた。
それにしても……
「なんで私の名前……」
深い意味はないのかもしれない。
他に名前が思いつかなかったのかもしれない。
に、しても……
「ど、どうしよう。……嬉しい」
顔がニヤけるのが止められない。
今日はなんて良い日だろう。
私はそんなことを考えながら、はたから見れば気持ちが悪いくらいの笑みを浮かべていたと思う。
すると、
「ニャウ」
ゴロゴロと黒猫と対照的に甘えるようにすり寄ってきた灰猫。
黒猫のいい人…もといいい猫だと言うなら……
「斎藤…よりも……」
一瞬のためらい。
そして、
「はじめ…?」
首を傾げる灰猫。
「あなたの名前は……一」
そっと頭を撫でてそう言うと、嬉しそうに「ニャァ」と鳴いた。
私も嬉しいけど恥ずかしいけど、やっぱり嬉しくてはじめ、はじめと連呼してみた。
だって絶対本人には呼べないし。
すると黒猫が私に毛を逆立てる。この猫はどうも嫉妬深いらしい。
「斎藤さんとはじめ両方なんてズルイ」
むうと膨れる私をほっておいてじゃれ始める二匹。
そんな二匹を見ながら、ポツリとこぼれた本音は、
「斎藤さんは……人間の一さんは私のなんだからね…」
言ったとたん恥ずかしさに悶絶して一人、頭を抱えた。
まさか、それらを本人が見ていたことは……
「ニャウ」
「ニャー」
二匹も知らない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ホワイトデーの副産物。
斎藤さんのホワイトデー話で猫を出したところ、収集がつかなくなってホワイトデー関係ねぇよってことになったので、
別にアップ。
斎藤さんが相手だと千鶴ちゃんが攻めっぽい。
ま、じゃないと話がすすまねぇんだよ。この人は!
沖田だたと勝手に進み過ぎてやべーことになっちゃうんですけどもね。
千鶴名前ネタをしたくて雪村呼び。これもまた萌えるな(自己満)
↓はおまけ
「はじめ」
聞こえた自分の名前に足を止めた。
見れば雪村が灰猫を撫でている。
……なぜか、妙に苛立つ。
さっきも咄嗟に雪村の手を掴んでまで止めてしまった。
しかも、千鶴と呼んでしまうとは……不覚。
「あなたの名前は……一」
楽しげに笑いながらそう言う雪村。
何故その猫の名前が俺と同じなのか。
いい名前が思いつかなかったのか。
深い意味はないだろうが……
雪村が何を考えてその名を付けたのか思案していると、また、雪村が『はじめ』と嬉しげに呼ぶ。
………何故俺の顔が熱いのか。
呼ばれているのは猫だとわかっているのに。
こんな顔を雪村に見られる訳にはいかないと木の陰に隠れ頭を冷やそうとした時、小さいながらも風に乗ったその声は俺の耳にしっかりと聞こえた。
「斎藤さんとはじめ両方なんてズルイ」
少し怒った様な拗ねたような声。そして……
「斎藤さんは……人間の一さんは私のなんだからね…」
「っ…」
思わず口を押さえた。が、
どうやら当分はこの熱が冷めてくれそうにはない……